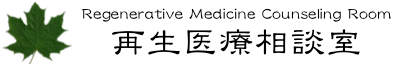- 2025.04.14
京都大学病院、Ⅰ型糖尿病の患者に対し、iPS細胞から作製した膵島細胞シートを皮下移植する臨床試験(治験)を実施
京都大病院は4月14日、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが分泌されなくなるⅠ型糖尿病の患者1人に対し、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作製した膵島細胞を薄いシート状にし、腹部の皮下に移植する臨床試験(治験)を実施したと発表した。患者は経過良好で既に退院しており、最大5年間にわたり経過観察します。
本臨床試験は、iPS細胞から作成された膵島細胞をシート状にする技術は京大iPS細胞研究所などが開発し、京大病院が医師主導型の治験を計画し、2024年8月23日付で学内で承認され、国の医薬品医療機器総合機構(PMDA)に9月2日付で申請されたものです。今回の治験は、本治療の安全性を確かめることが目的です。
計画では、健康な人のiPS細胞から膵島細胞をつくり、数センチ四方のシート状にして、複数枚を患者の腹部の皮下に移植する。20歳以上65歳未満の重症患者3人が対象で、まずは1年にわたり安全性を確認する。マウス実験では有効性が確認されています(japan today)。この治験に関する詳細な情報や進捗状況については、京都大学医学部附属病院の公式発表などでご確認ください。(京都大学医学部病院・ニュース「iPS由来膵島細胞シート移植に関する医師主導治験」の開始について)
- 2025.04.10
1型糖尿病患者の皮下脂肪から作ったインスリン産生細胞、自身に移植…徳島大病院で夏にも治験
徳島大病院 消化器・移植外科の池本哲也医師らは、皮下脂肪細胞から採取した脂肪由来幹細胞から再生医療技術で、“膵島”(インスリン産生細胞・IPC)を作成する研究を2018年度から開始した。1型糖尿病患者の脂肪由来幹細胞から作成した膵島をマウスや豚(腸間膜内に移植)に移植し、移植2週間後から血糖が正常化し、1年以上持続して効果を確認できた。局所麻酔した患者から皮下脂肪組織を1グラム採取し、分離・精製して脂肪由来幹細胞とし、培養・分化・成熟させ、IPCを作製し、腹腔鏡手術で患者の腸間膜内に注入する「IPC自家移植」する方法を確立したと3月24日発表した。今夏にも1型糖尿病患者の根本的治療を目指す治験を始めると発表した。池本医師らは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った細胞シートの移植を計画する京都大病院と比較して「患者自身の細胞を使うこの治療法は(遺伝子導入などがないため)、安全面でアドバンテージがある」としている。(読売新聞オンライン2025.04.10)
- 2024.04.26
遺伝子改変されたブタの腎臓移植、今度は心臓ポンプを装着した患者で成功!
再生医療において臓器丸ごとの再生は今のところ困難であるが,移植医療の分野では臓器不足を異種移植で乗り越えようとする試みがなされている。「ヒトとブタの間の進化的な距離1億年(ハーバード大学医学部教授のンディープ・メフラ)」を乗り越えてニューヨーク大学ランゴン医療センターで遺伝子改変されたブタの腎臓(+胸腺)移植が実施され、54歳の女性は2人目の生存者となった(2024年4月12日)。ニューヨーク大学の研究チームはゲノム編集において「less is more(少ないほうがいい)」というアプローチをとり、ゲノム編集の箇所を増やす代わりにブタの胸腺を同時に移植することで免疫不適合を抑えている。ブタから腎臓を採取する2カ月前に胸腺を首から取り出し、腎臓の下に配置した。その後、胸腺は腎臓と一体化し、腎臓と一緒に移植できるようにした。臓器不足に直面する移植医療は、新たな手法で拒絶反応を防ぎ、また歩を進めた様である。(WIRDE EMILY MULLIN SCIENCE2024.04.25)
- 2024.04.19
再生医療でアルツハイマー病のアミロイドを分解できる!
アルツハイマー病では脳内にアミロイドが沈着します。この間葉系幹細胞はこのアミロイドを分解する力を持っています。Yamagishiらは、アルツハイマー病患者自身の脂肪組織由来幹細胞を培養しそこにアミロイドを分解する酵素=ネプリライシン活性があることを発見しました1。アルツハイマー病の脳ではネプリライシン活性が低下していることが報告されています。これを、患者さん自身の細胞で“再生”できれば理想的な治療に繋がると期待されます。レケンピ(レカネマブ)はアミロイドを除去する抗体薬ですが、脳浮腫や脳出血のリスクがあります。ご自身の幹細胞投与での脳浮腫、脳出血の報告はありません。(Neurosci Lett. 2024 Mar 10:825:137705. doi: 10.1016/ j.neulet.2024.137705. Epub 2024 Feb 28.)(PubMed > Shigematsu K, Komori N, Ideno M, Yamagishi H. Evaluation of neprilysin activity in adipose-derived stem cells from alzheimer's disease patients. Neuroscience Letters. 2024:137705)
- 2023.03.30
今話題のOpenAI chatbotのChatGPTに再生医療の説明をお願いしました。次の様な説明が帰ってきました。素晴らしい回答だと思いますね。この文章をAIが日本語で,一瞬で作成しました。すごい世の中に!
再生医療とは、人間の体内に存在する細胞や組織を再生・修復することで、病気やけがの治療を行う医療のことを指します。具体的には、幹細胞や組織工学技術を用いて、細胞や組織を再生することができます。
再生医療は、がんや心臓病、神経変性疾患などの難治性疾患や、けがや外傷の治療に期待が持たれています。また、従来の医療では難しい臓器の再生や、細胞治療による新しい治療法の開発も進んでいます。
ただし、再生医療はまだ実用化までには多くの課題が残されており、安全性や有効性の確保、高コストなどの問題があります。今後も継続的な研究と開発が求められる分野です。
- 2023.03.09
"ミューズ細胞の開発中止(三菱ケミカルグループ)"(日経新聞2023年2月14日16:25より) 【三菱ケミカルグループは2月14日、再生医療に使う「Muse(ミューズ)細胞」の開発を中止すると発表しました。最新の臨床開発状況から、事業化し収益に貢献するまでに時間がかかると判断しました。ミューズ細胞は再生医療に使う技術で、これまで急性心筋梗塞や脳梗塞など7つの疾患の治療に役立つとみて、臨床試験(治験)を進めてきました。ミューズ細胞は体のさまざまな臓器にあり、健康な人から採取した間葉系幹細胞から取り出して培養し、患者に点滴で投与すると、脳梗塞などで損傷した部位に集まり、必要とされる細胞に育って患部の修復に役立つとされています。】>(開発研究が中止されたことで再生医療の実用化が遅れる懸念が生じました。ミューズ細胞は2010年に東北大学の出沢真理教授が報告した細胞です。2001年にZukらが発見した脂肪組織由来幹細胞(Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, et al. Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-based therapies. Tissue Eng. 2001;7(2):211-28.)も様々な細胞への分化能を持ち損傷部位に集まって修復を促進することが知られています。再生医療の進展に期待したいものです)
- 2022.06.09
"新しい生分解性ゲル+細胞は「心臓発作による損傷を修復する」可能性がある" マンチェスター大学の研究者たちは、心臓の自己修復を助ける解決策として鼓動する心臓に直接注入することができるゲルを開発しました。ゲルとともに注入した細胞が新しい組織を育てます。ゲルはその細胞が組織を再生するための足場として効果的に機能しました。これまで、心不全のリスクを減らすために心臓に細胞を注入した場合、その場所にとどまって生き延びたのはわずか1%でした。しかし、このゲルのおかげで心臓に移植された細胞は生き残ることができるようになり、所定の位置に定着しました。英国心臓財団(BHF)の支援を受け、この研究を主導したKatharine Kingは、「このゲルは、損傷した心臓の再生を助ける、将来の細胞ベースの治療法の有効な選択肢になり、心臓発作後の機能不全の心臓を修復するのに役立つ可能性は非常に大きい」と述べています。この新しいゲルは、ペプチドから作られており、ストレスを受けると液体のようにふるまい、細胞と混合して心臓に注入され、その後ペプチドが再集合して固体となり,注入細胞の足場として機能するようです。全世界で死因第1位、日本での死因第2位の心疾患の有益な治療法となることが期待されます。(TIMES Series:"New biodegradable gel could ‘repair damage caused by heart attack", 8th June 2022、The Guardian:Andrew Gregory, "Gel that repairs heart attack damage could improve health of millions", 8 Jun 2022)
- 2022.03.11
"腎臓由来の細胞外マトリックスを利用してブタの体内で部分切除した腎臓の再生に成功" 慶應大学医学部外科学教室と国立研究開発法人産業技術総合研究所のグループは、部分切除したブタの腎臓切断部に別のブタ腎臓から「脱細胞」して作成した細胞外マトリックス(コラーゲン)を縫合し,細胞増殖の足場として腎臓を体内で再生させることに成功し、その内容をnpj Regenerative Medicineに投稿・掲載されました(npj Regenerative Medicinevolume 7, Article number: 18 (2022) )。腎臓は静脈、動脈、ネフロン、尿管から構成される複雑な臓器で一般に再生することがない臓器とされています。本研究の報告では、細胞マトリックス移植28日後には腎臓を構成するネフロン、血管、尿管などの構造まで再現され、マトリックス内にはネフロン再生を導いたSall1、Six2、WT-1などの腎前駆マーカーが発現し、内部には活発な血流がCTにより観察されました。腎臓の再生医療は,現状ではiPS細胞からネフロン前駆細胞を誘導分化させるアプローチなどが取られていますが、まだ腎臓の実用的な再生の段階には至っていません。本研究報告は従来の再生腎臓を作るというアプローチとは異なるものですが、「脱細胞」して作成した腎臓の細胞外マトリックスを細胞増殖と分化の足場にして腎臓の複雑な構造を再生することに成功した意味は大変大きいと考えられます。通常、細胞を培養して増殖させるにはコラーゲンなどを細胞の足場とする必要があり、またその増殖が停止した段階から分化が始まります。従来の再生腎臓の作成に腎臓の細胞外マトリックスなどの足場の利用などの検討も可能かもしれません。
- 2022.01.11
"成熟膵島細胞を増やすことに成功 ~糖尿病の根治に向け、新たな再生治療法の可能性を発表~" 東京大学、京都大学、愛知医科大学らの研究グループは、出生前後に増殖する膵島細胞で高発現するMYCLに着目し、MYCLを働かせて生体内外の成熟膵島細胞に自己増殖を誘発できることを明らかにし、「Nature Metabolism」(オンライン版2022年2月10日(英国時間))に掲載されました。また、本研究については東京大学医科学研究所のプレスリリース(2022年2月11日)に図入りで分かりやすく掲載されました。マウスのストレプトゾトシン(STZ;膵島β細胞を特異的に破壊する薬剤)を投与による糖尿病モデルマウスでの生体内MYCLの発現誘導や単離した膵島細胞をMYCL遺伝子により増幅させ移植した糖尿病モデルマウスにおいても血糖値を改善させました。
>従来、成体の膵島(細胞)は分裂しないものと認識されており、ヒトや動物の膵島を分離・精製し,膵島そのものや免疫隔離容器に密閉して、血糖の調節を目標に異種や同種移植への試みが行われてきました。今までのところ、これらの試みは再生医療の分野で十分な成果を上げていませんでした。今回の膵島細胞そのものを生対外で増殖して移植したり、生体内でMYCL遺伝子誘導にて膵島細胞を増殖させて糖尿病モデルマウスで血糖値を改善したことは、糖尿病治療において大きな可能性を感じさせ、糖尿病のMYCL遺伝子増殖細胞移植療法やMYCL遺伝子治療の可能性を示唆しました。今後細胞や生体での長期的なMYCL遺伝子誘導の影響の確認などを経て臨床応用されることを期待します。
- 2022.01.11
"臍帯血点滴投与で脳性麻痺が改善" 米国デューク大学小児科では脳性麻痺がある白血病の子どもに凍結保存していた自身の臍帯血による治療を行ったところ、白血病だけでなく脳性麻痺も改善がみられました。米国では2019年時点で2500人を超える脳性小児麻痺(虚血性脳症)の方が自己臍帯血治療研究に参加しています。
日本では高知医科大学の前田長正教授らが自己臍帯血由来幹細胞による脳性麻痺の治療に取り組んでいます。最近の報道によれば、1~7歳未満の脳性麻痺の子供11人がこの再生医療をうけ、運動機能障害や知的障害が改善したとのことです。点滴投与された幹細胞が病変部位である脳に働いて症状を改善したと考えられます。早い人では投与翌日から投与後半年間にわたって改善し、リハビリと併用すれば3年間はその効果が持続するとのことですから、今後この治療研究に期待が持てますね。
- 2021.12.10
慶應大学の岡野栄之教授らは、神経細胞に分化しやすい性質を持つiPS由来細胞であるhiPSC-NS/PCsをネズミの脊髄に移植しました。移植したhiPSC-NS/PCsの化学的刺激が神経同士の相互作用を増強することを試験管で観察しました。移植されたネズミの脊髄では、神経関連遺伝子や蛋白の発現が増え、脊髄の萎縮が防げたと報告しました(Cell Reports Volume 37, Issue 8, 23 November 2021, 110019)。脊髄損傷の治療に幹細胞移植が有用であることが示されたと述べています。
- 2021.10.23
臓器移植は多くの人々の命を救う可能性がありますが、利用可能な人間の臓器には限りがあるため、ドナーが見つかるまで何年も待たなければならなかったり、移植が間に合わず死亡してしまったりすることが問題となっています。近年では、臓器不足を解決するために「ブタの臓器を人間に移植する試み」が模索されており、新たにニューヨーク大学(NYU)ランゴーン・ヘルスの外科チームが「遺伝子組み換えを行ったブタの腎臓を人間の体に接続し、老廃物を除去させる実験に成功した」と発表しました。>ブタの臓器を使った治療は1920年代のブタインスリンが有名です。ブタと人のインスリンではアミノ酸が一つ違うだけです。1979年にはそのアミノ酸を取り換えることによって人インスリンの合成に成功しました。臓器としてはブタの心臓弁が今でも使われています。ヒヒではブタ心臓を移植して年余にわたる生存が確認されていますから、理論的には応用可能かもしれません。ブタ腎臓も治療に使える可能性が示された研究でしょう。そうはいっても、臓器となればアミノ酸一つを変えて人と同じものにすると言う訳にもいかないので、再生医療で人の腎臓が作れるようになれば良いですね。
- 2021.10.16
尿失禁が再生医療で改善!尿失禁(尿漏れ)は前立腺全摘出後に起こりやすく、膀胱の出口の尿の蛇口の役割を果たす「尿道括約筋」が弱まることが原因だと言われている。南部徳洲会病院(八重瀬町、服部真己院長)やバイオベンチャーのフルステム(那覇市、千葉俊明社長)などは10日、前立腺を全摘出した後に尿漏れの症状がある男性患者2人に対し、皮下脂肪から抽出した幹細胞を括約筋に注射する手法で再生医療を実施し、成功したと発表した(琉球新報 尿失禁が再生医療で改善 沖縄で初、前立腺全摘出の患者に成功 南部徳洲会など 2021年10月13日)。>脂肪組織由来幹細胞を含めた間葉系幹細胞には”ホーミング作用”と呼ばれる「病巣に集まる性質」があります。括約筋に直接投与しなくても例えば点滴投与で同じ様な効果がでるとより安全で容易に治療できるようになるかも知れません。
- 2021.10.01
筋萎縮性側索硬化症(ALS)について、iPS細胞を活用して見つけ出した薬を実際の患者に投与する初期段階の治験で症状の進行が抑えられたと京都大学iPS細胞研究所の井上治久教授らのグループが発表しました(https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/211001-000000.html)。グループはALS患者のiPS細胞から作り出した神経細胞を使って実験などを行うことで、「ボスチニブ」という白血病の薬がALSの進行を抑える可能性があることを突き止め、2021年3月から、国の承認を受けるための治験を進めています(https://rctportal.niph.go.jp/s/detail/um?trial_id=UMIN000036295)。>ボスチニブはSrc/c-Abl阻害薬で慢性骨髄性白血病の治療薬です。Src/c-Ablはチロシンキナーゼで幾つかの神経変性疾患に関与していることが知られています。ボスチニブはALSモデルマウスの脊髄においてミスフォールドしたSOD1の蓄積を減少させることが分かっています(Science Translational Medicine, 9, eaaf3962 (2017)>新着論文レビュー:今村・井上「Src/c-Abl経路は筋萎縮性側索硬化症の潜在的な治療の標的である」(2017))。
- 2021.07.04
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、初期症状から3〜5年の平均余命を伴う進行性の衰弱性神経変性疾患です。自家脂肪由来間葉系幹細胞(ADSC)を受け、7年間追跡されたALSの症例が報告されています。46歳の男性は2009年にALSの診断が確認され、彼のALS機能評価尺度-R(ALSFS-R)は43で、症状は急速に進行し、食事中に咳と窒息を起こしました。 2013年以降、患者は自家ADSCの合計6回の静脈内注入を受け、投与後すぐに症状改善に気づきました。彼は階段を降りるのに苦労したが、咳、構音障害、または嚥下障害なしで健康を維持し、ALSFS-Rは45になりました。患者は、この報告の時点までにADSC療法後7年間、発症時から10年以上健康でした。>本症例は、ALS患者に自家ADSCの投与は安全で有用である可能性を示唆していますが、結果を他のALS患者に一般化するためには更なる症例が必要です。
- 2021.06.28
慶応大学は、人のiPS細胞(人工多能性幹細胞)を使って脊髄損傷を治療する臨床研究について、患者の受け入れを始める、と発表しました。1年かけて安全性や有効性を検証するとのことです。>尚、札幌医科大学の本望らは、13名の脊髄損傷患者に自己間葉系幹細胞投与し安全性と有効性が認められたと報告しています(O Honmou et al. Clinical Neurology and Neurosurgery Volume 203, April 2021, 106565)。
- 2021.03.14
札幌医科大学の本望修教授らの研究グループは、脊髄損傷の患者13人に対し、患者自身の体から取り出し培養した間葉系幹細胞(MSC)を静脈から投与し、MSC投与後6か月で、13人の患者のうち12人にASIAグレード(アメリカ脊髄障害協会機能障害尺度)に基づく神経学的改善が見られ、13人全員に問題となる副作用はなかったと報告しました。この研究は盲検化されておらず、プラセボ効果または内因性回復または観察者バイアスの寄与を排除しないことを強調していますが、殆どで大幅な改善といえるもので、特に首から下が麻痺し寝たきり状態だった患者2人に関しては、装具の助けを得ながらの食事、車椅子の運転、タブレット操作ができるようになるなど劇的な改善がみられたという。殆どの症例で激減な改善を示し、詳細はClinical Neurology and Neurosurgeryに投稿・掲載された。>脊髄損傷や認知症などに対してもMSC投与の有効性の報告が蓄積されてきており、その詳細な作用機序の解明が待たれる!
- 2021.02.16
名大は再生能力の高いアフリカツメガエルのオタマジャクシの遺伝子の網羅的発現解析から神経転写因子の「Neurod4」を発見し,神経幹細胞に感染しやすいリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルスのエンベローブ(ウイルスの殻)にレトロウイルスの中味を入れた遺伝子導入用のハイブリッド型のベクター(運び屋)ウイルスを利用して脊髄損傷したマウスの脊髄内の損傷部位までNeurod4を届け,幹細胞に遺伝子を入れることで神経再生に成功し,新生運動ニューロンと既存のニューロンがシナプスを形成することで下肢機能が改善されたと発表した。>体性幹細胞を遺伝子的に修飾して利用する新しい手法だけど,安全性は?
- 2021.02.06
阪大の研究チームがiPS細胞から目の結膜細胞を作ることに成功し、ドライアイなどに対する創薬への活用が期待される(セル・リポーツ電子版に掲載)。また、米ボストン大の研究チームはiPS細胞から肺胞の細胞を作製し、新型コロナウイルス感染実験から新たな治療薬の候補物質を5種類特定したと発表した(モレキュラー・セルに掲載)された。>創薬に利用されるiPS細胞に大いに期待!
- 2021.01.23
イスラエルの医療技術企業CorNeat Visionが開発した生物模倣素材で構成され人工角膜が初めて、失明した患者に移植され、視力を取り戻すことに成功したと発表しました。ドナー不足を解消するCorNeat Vision KProは合成非分解性ナノファブリックが眼の組織に溶け込み、変形したり、不透明化した角膜の代わりになります。>未来の再生医療では人工的に作られた組織・臓器と生体が複合するのかも?
- 2021.01.20
不可逆的な増殖停止を示す老化細胞は加齢に伴い生体内に蓄積し、老齢マウスから遺伝子工学的に除去すると健康寿命の延伸や加齢関連疾患の病態改善が認められる。東大、九大、新潟大、慶應義塾大、国立長寿医療研究センターなどのグループは、グルタミン代謝酵素GLS1阻害剤の投与によりさまざまな組織・臓器において老化細胞が死滅し、加齢現象が有意に改善し、加齢関連疾患モデルマウスでは肥満性糖尿病、動脈硬化、非アルコール性脂肪肝の症状が緩和されたと報告した。(>掲載されたサイエンスへ)>グルタミンは増殖する細胞では必須成分
- 2020.12.18
認知症の原因の多くを占めるアルツハイマー型認知症の患者に対し、自家脂肪幹細胞の投与により多くの患者で認知機能に改善が見られたとする研究結果を、京都府立医大の名誉教授などでつくるグループが発表しました。同グループでは、現在、パーキンソン病の患者に対しても同様の臨床研究を行っていて、症状の改善が見られているとしている。>この分野の新規医薬品開発が難航する中,自家脂肪幹細胞の投与に期待
- 2020.12.13
根本的な治療法が心臓移植しかない拡張型心筋症の小児患者に、培養自家幹細胞を移植する「心筋再生医療」に取り組む岡山大病院のグループは、ブタによる研究で移植した幹細胞が「抗炎症作用を持つマイクロRNAを含む細胞外小胞」を分泌し、それを傷んだ心筋が取り込み、ダメージを修復するとともに、血管の新生を促していたことを突き止めた。>まだ不明な点が多い体性幹細胞投与のメカニズムに一石を投ずるかも(再生医療用語集>マイクロRNA)
- 2020.11.15
AI(人工知能)とiPS細胞(人工多能性幹細胞)を組み合わせ、新薬の候補物質を探す手法を開発したと、京都大iPS細胞研究所などの研究グループが発表し、この手法を用いて筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療薬の候補も見つけたという。>現時点でiPS細胞の利用方法としては最も実用的かも
- 2020.10.30
岡山大大学院医歯薬学総合研究科の山下徹講師らは筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発症させたマウスに、ヒトの骨髄から採取した幹細胞「Muse細胞」を投与すると、症状の進行を遅らせる効果があることを確認したと発表した。>脂肪幹細胞のALS患者への投与は実施されています
- 2020.10.15
京都大の関連財団が備蓄するiPS細胞から作った視細胞のもとになる網膜のシート(直径約1ミリ)を、目の難病「網膜色素変性症」の患者に移植する世界初の手術を神戸市立神戸アイセンター病院が実施した。>後頭葉に繋がるかが鍵!
- 2020.09.16
肺炎を起こしたマウスの鼻から、「間葉系幹細胞」という細胞を投与することで、肺が硬くなり呼吸がしづらくなる「線維化」の進行を抑える。>静脈投与を含め新型コロナ患者への投与が世界中で試みられているようです